
⇧私が捕獲した初の鹿さんです⇧
私は猟師として田舎で約三年暮らしていました。
とはいっても【専業猟師】ではなく、ほかの仕事もしながら猟師をする【兼業猟師】としてくらしていました。
はっきり言って猟師を専業の仕事としてやっていくのは非常に難しいです。
今回は「猟師がなぜ専業でやっていくのが難しいか」について書いていきます。
猟師としての収入源

猟師の収入源は大きく3つに分けられます。
- 有害鳥獣駆除による報奨金(または報酬)
- 捕獲した鳥獣(ジビエ)の肉や皮、角などの販売
- その他
有害鳥獣駆除による報奨金(または報酬)

・イノシシ、シカ、サルなどの有害鳥獣を捕獲、駆除することで自治体から報奨金が支払われます。
・金額は自治体や捕獲した鳥獣の種類によって異なります。(頭あたり数千円~数万円)
※私の活動していた場所ではシカ一頭で数万円、イノシシ一頭で1万円強、サル一頭で約3万円でした。
・多くの場合、地域の猟友会に所属し、「鳥獣被害駆除員」などの隊員として活動することが必要です。
捕獲した鳥獣(ジビエ)の肉や皮、角などの販売

⇧むさしが見つけてきた鹿の角⇧
- 捕獲した鳥獣の肉を食肉(ジビエ)としてレストランや食肉加工業者、直売所などに販売します。高品質な肉の処理には専門の技術や設備(食肉処理業・食肉販売業の許可など)が必要です。
- シカの角はインテリアやアクセサリー、漢方薬の素材として、皮は革製品の素材として販売されることがあります。
犬のおやつとして加工して販売したりすることもあり、フリマアプリやネットオークションでの取引も見られます。
※⇧これが一番簡単で成果につながります。
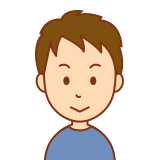
ですがどれも最近では需要が右肩下がりです。
その他
- 狩猟ガイド・自然体験の提供

自身の知識や経験を活かし、狩猟体験や自然体験プログラムを企画・提供することで収入を得るケースもあります。
※村であれば、地域おこしとして協力してくれる可能性もあります。
- 情報発信による収入

狩猟の様子や経験をブログやYouTubeなどで発信し、広告収入やファンへの商品販売などで収入を得るケースもあります。
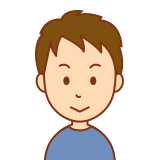
私の理想です。いつかは叶えたい
- 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者としての給与
指定管理鳥獣(シカ、イノシシなど)の捕獲を公共事業として請け負う法人などに雇用され、給与を得る「サラリーマン猟師」という働き方もあります。
全体としてはまだ少数派です。
※これは知りませんでした。
猟師・なぜ専業でやっていけない?
日本の猟師の多くが専業として生計を立てるのが難しい主な理由は以下の4つ
収入源の不安定さ
猟師の主要な収入源の一つは、有害鳥獣駆除に対する自治体からの報奨金です。この報奨金は自治体の財政や、その年の鳥獣被害の状況、被害対策の方針によって金額や制度自体が変動する可能性があります。
地域によっては報奨金が出ない、あるいは非常に安価である場合もあり、安定した収入源とは言えません。
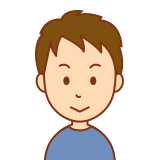
私の地域はかなり報奨金が高い地域でした。
ジビエ販売の難しさ
捕獲した獣肉(ジビエ)を販売するには、高い品質管理(衛生的に問題ない場所で、適切な止め刺し、迅速な血抜き、衛生的な処理)が求められます。
販売するには、食肉処理業や食肉販売業の許可が必要であり、そのための設備投資(解体処理施設)が非常に高額になります。
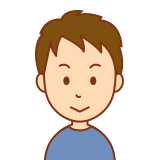
基本新人猟師が解体したお肉は衛生上の観点から、
よほどの人脈でもないかぎり買い手が付きません。
食べてみたいという知人にお肉を譲り、
お小遣いとしてもらっていました。
これらのハードルから、個人で安定的に高値で販売できる猟師は限られています。
高い経費と初期投資
初期投資(銃、罠など)
猟銃の購入費、銃の所持許可にかかる費用、罠の購入費、狩猟免許の取得・更新費用などがかかります。特に箱罠などは一つ数十万円と高価です。
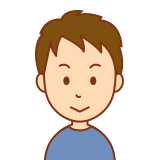
猟銃は無くても猟師になれるので、費用面からも初めは罠猟から始めることをお勧めします。
維持費とランニングコスト
弾薬代、車の維持費、山に入るための装備費、猟友会費、保険料など、狩猟を続けるための経費が継続的に発生します。
特に獲物が獲れなかったりジビエとして販売できなかったりすると、これらの経費がそのまま赤字となります。
狩猟活動の制約
狩猟法により、一般の狩猟は原則として11月15日から翌年3月15日までと、期間が限定されています。
自治体の許可による有害鳥獣駆除は通年可能な場合もあります。
⇧専業とするには、基本有害鳥獣駆除員となり収入を賄う必要があります。

自治体によって違いますが、こんな感じの濃いオレンジ色のベストを着用します。
背中に「有害鳥獣駆除員」と書かれています。
危険性、体力、技術
狩猟は自然の中での重労働であり、常に危険が伴います。
体力の消耗や怪我のリスクも高く、長期間安定して稼ぐには長年の経験と高度な技術が不可欠です。
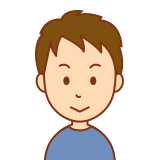
一度狩猟中にイノシシが山の斜面上から突っ込んできたことがあります。
マジで死ぬかと思いました。
その数日後、他県で罠にかかったイノシシに突進され亡くなられたというニュースを、見ました。
これらの理由で、
多くの猟師は「有害鳥獣駆除による報奨金」や「ジビエ・副産物の販売」を副収入とし、
本業(農業、会社員など)で生計を立てる「兼業猟師」という形が主流となっています。
まとめ:猟師は専業ではなく副業でやれ
いかがでしたでしょうか?
読者さんの中には「猟師になりたい!」「猟師になって田舎でのんびり暮らしたい」と考えている方もいるかもしれません。
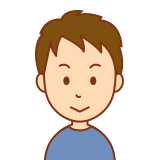
私は今でもそうです。
ですがはっきり言います。
猟師は専業よりも副業(兼業)として行うのが、現実的かつ賢明な選択です。
専業として高い収入を得るには、大規模なジビエ処理施設への投資や狩猟ガイドなど多様な事業展開が必要となり、ハードルが高すぎます。
気候や体調が優れず獲物が取れないと収入が「ゼロ」になるというのはリスクが大きすぎます。
そのため、まずは本業の安定収入をベースに、狩猟を副業としてリスクを抑えながら活動していくのがおススメです。
それでは今日はこんなところで!
よかったら次の記事も見てください!(^^)

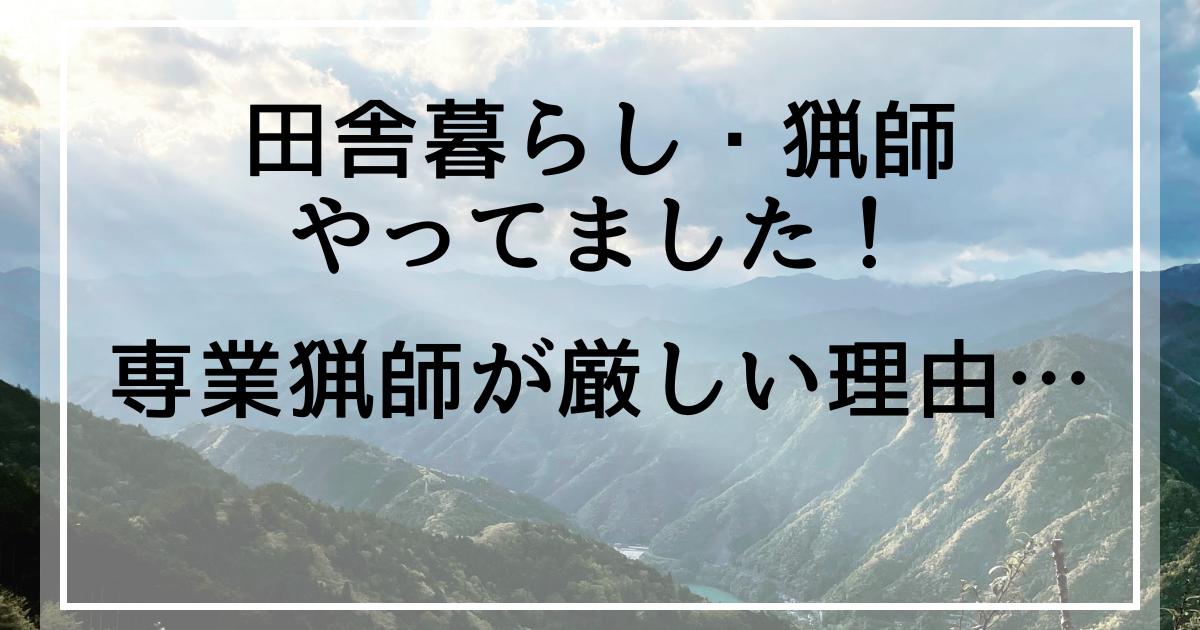
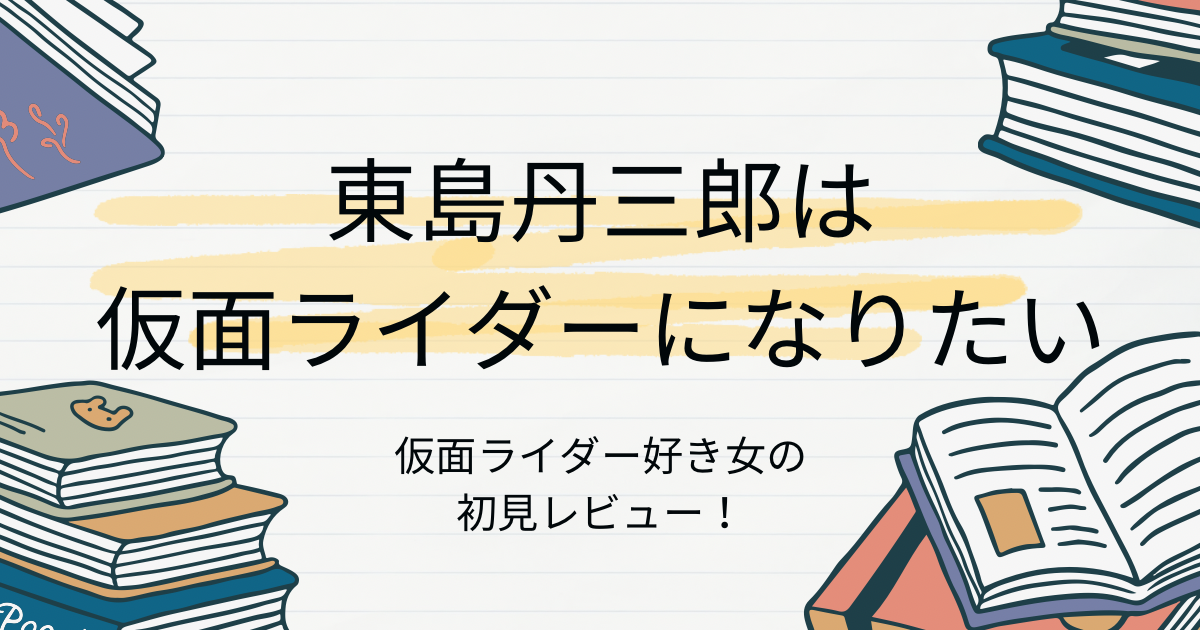

コメント