うちの犬は大丈夫?
こんばんは!おけらファミリーです!
今日はねーさんがおしゃべりします!
実家の柴犬・レオは、尿路結石の1つである、ストルバイト結石です。
いろいろ大変なことがあります。
今日は、早期発見がとても大事な病気なので原因・症状・予防法を紹介します!
チェックリストを先に出しておきます!
これらのサインを見逃さず、少しでも異変を感じたらすぐに動物病院で尿検査を受けましょう。
• 頻尿: トイレに行く回数が急に増えた
• 血尿: おしっこに赤みが混ざっている
• 排尿姿勢: おしっこを出すのに時間がかかったり、痛そうにしている
• 飲水量: 水を飲む量が増えた、または急に減った
• 結晶: おしっこやトイレシートの表面がキラキラ光って見える(結晶の可能性)
愛犬のオシッコ、いつもと違う?気になる「ストルバイト結石」
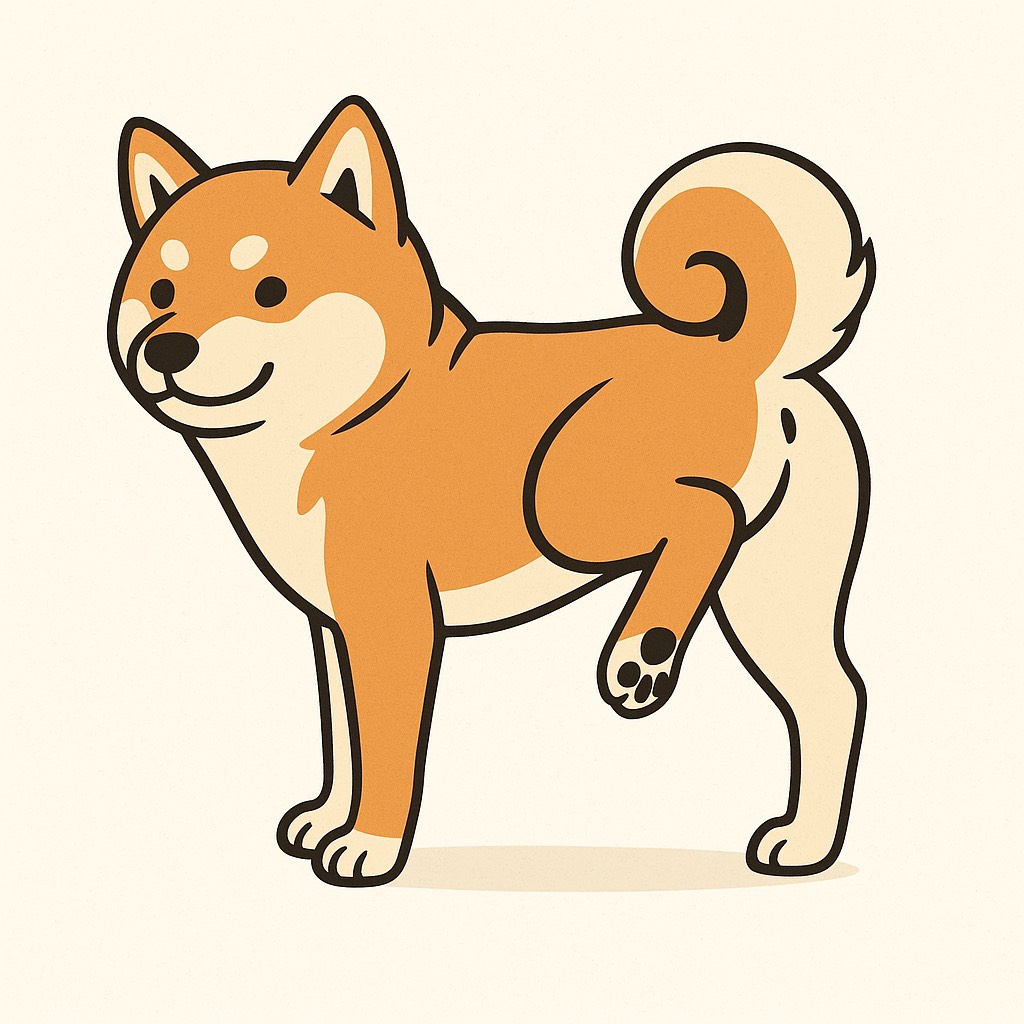
愛犬のおしっこの様子って見ていますか?
「頻繁にトイレに行く」「オシッコの色が赤い」…もしそんなサインがあったら、要注意です。
もしかすると、それはストルバイト結石かもしれません。
ストルバイト結石は、犬の尿路疾患の中でも比較的多い病気です。
飼い主さんが日頃から気をつけるべきこと、いざという時の対処法について、経験者である私が分かりやすく解説します。
【原因と症状】ストルバイト結石ってどんな病気?

※ストルバイト結石の正体と発生のメカニズム
ストルバイト結石は、尿中のリン酸アンモニウムマグネシウムというミネラル成分が結晶化し、結石となって膀胱などに留まりおしっこが出来なくなるという病気です。
放置してしまうと、大きい結石になってしまい手術をしないといけなくなります。
一度病院で、直径5cmほどの結石を見せてもらいました。
実はそれは大きなワンちゃんではなく、トイプードルから摘出されたものでした。
最も大きな原因の多くは、細菌による尿路感染症(膀胱炎)の併発です。
細菌が尿中の成分を分解し、尿のpHをアルカリ性に傾けることで結石ができやすくなります。
その他、水分摂取量の不足による尿の濃縮や不適切な食事が関係することも。
pHは高いほどアルカリ性が強く、
健康的なワンちゃんであればpHは「6」ぐらい、レオは最初「9」でした。
尿を顕微鏡で確認させて頂きましたが、どこを見ても結晶がすごかったです。
見逃さないで!愛犬が出す尿路結石のサイン(症状)
初期は無症状なこともありますが、
結石が刺激となって炎症を起こすと以下のような症状が見られます。
・頻尿(トイレに行く回数が増えるが、少量しか出ない)
・血尿(オシッコに血が混じる、ピンクや赤っぽい色)
・排尿時の痛み(排尿を嫌がる、鳴く、陰部を気にして舐める)
特に危険なのは、結石が尿道に詰まってしまう「尿道閉塞」です。
オシッコが全く出ない場合は命に関わる緊急事態なので、すぐに動物病院へ行って下さい。
レオは少しですが血尿が出ました。
すぐ病院に行き、尿路結石が発覚しました。
よくよく思い返すと↑のよくな症状を見ると、思い当たる点がありました。
【予防と対策】ストルバイト結石から愛犬を守る3つの柱

最重要!獣医師と相談する「食事療法(療法食)」
ストルバイト結石は、適切な食事療法で溶解が期待できるのが特徴です。(※シュウ酸カルシウム結石とは異なります)
基本は、低マグネシウム・低リンで、尿を弱酸性に保つように成分調整された療法食への切り替えです。
自己判断でフードを選ぶのではなく、必ずかかりつけの獣医師に相談し、愛犬の状態に合った療法食を処方してもらってください。
療法食を与えている間は、結石の原料になるマグネシウムやリンが多いおやつや人間の食べ物(煮干し、チーズ、レバーなど)は厳禁です。
レオも、療法食をあげています。
意識的に行いたい「水分補給」で尿を希釈する
水分摂取量を増やすことは、尿を薄め(希釈)、結石の形成を防ぐために非常に重要です。
ドライフードからウェットフードに切り替える、または混ぜる。
ウエットフードの療法食もあります。
療法食は選択肢が少なく、食いつきがあまりよくないワンちゃんは苦労されるかもしれません。
レオもあまり食いつきが良くなく、療法食へ変更する際はかなり心配しましたが
今の療法食は良く食べてくれています。
水飲み場を増やし、常に新鮮な水を用意する(複数の場所に置くのも有効)。
ぬるま湯や、鶏の茹で汁(無塩)などで水の飲みやすさを工夫するのもおすすめです。
日常の習慣で予防する(排泄と健康チェック)
トイレの回数を増やし、排泄を我慢させない環境づくり。
特に留守番や外でしかトイレをしない子の場合は、対策が必要です。
散歩中にオシッコの量や回数、色をチェックする習慣をつけましょう。
定期的な尿検査(かかりつけ医での検診)で、尿pHや結晶の有無を確認することも予防につながります。
レオは、外でしかしないワンちゃんなので
仕事行く前や帰ってからすぐにおしっこだけでもさせに行くようにしています。
レオは、爪切りが難しい箇所があり一カ月半ぐらいのペースで病院で爪切りがして頂くので
そのタイミングで、尿検査もしてもらっています。
早期発見・早期治療が鍵!再発防止のために

ストルバイト結石は治療で溶けても、再発しやすい病気です。
結石がなくなった後も、獣医師の指示に従い、予防のための療法食や定期的な検診を続けることが、再発防止に繋がります。
「ちょっとおかしいな」と思ったら、ためらわずに動物病院を受診することが、愛犬の健康を守る早期発見の鍵です。
まとめ:愛犬の健康は日々の観察から
犬のストルバイト結石は、早期に対処すれば改善が見込める病気です。
大切なのは、日々のオシッコチェックと、適切な食事管理。
愛犬が快適に過ごせるよう、今日からできる予防を実践していきましょう。
不安なこと、疑問なことがあれば、必ずかかりつけの獣医師に相談してくださいね。
レオは、今ではpHも「7」まで下り元気に過ごしています。
ですが、安心はせず散歩の際にはおしっこを気にかけ、ご飯も療法食をあげています。
一生付き合っていく病気なので、
大変ですが悪くならないように、変化があった時はすぐに気付いて病院に連れていくいう感じで
それからも付き合って行こうと思っています!
今日はここまで!
最後までお読み頂きありがとうございました!


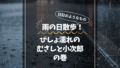
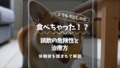
コメント